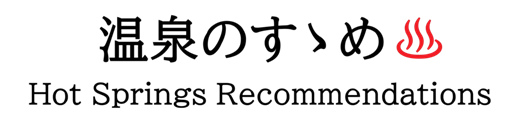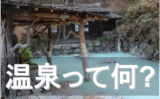世界と比べても「温泉大国」である日本。
はるか昔から開湯している温泉も多くあり、温泉は日本の古き良き文化の一つ。
そんな日本には、いったいどれくらいの温泉があるのか、どの地域が多いのか分かりますか?
今回は
- 日本の温泉の数
- 温泉が多い地域
- 温泉の色について
など、温泉について意外とあまり知られていない情報を紹介していきます。
「温泉が多い地域はどこ?」「温泉の色ってどうやって作られてるの?」こんな疑問を持っている方は是非最後までご覧ください。
温泉の分布と色について
温泉の数と源泉の数は全国でどれぐらい?
まずは冒頭にお話しした、全国の温泉の数について。
少し情報が古いですが、平成23年度の統計では宿泊施設が1軒以上ある場所を温泉地として、全国で「3108か所」の温泉地があります。
宿泊施設数は1万3754軒、宿泊者数は年間で延べ1臆2006万人余りに上ります。
これは日本国民1人が平均して年に一度は温泉に行って泊まっているという計算になります。
今は外国人の宿泊者も多いので最新の情報は異なるでしょうが、温泉が日本人にとって身近であるというのが分かりますね。
また、温泉の源泉数について。
こちらは全国に2万7531あり、温泉開発により大幅に増加しています。
そこからの湧出量(揚湯量も含む)は毎分268万1673Lに達し、これはドラム缶(200L)に換算すると毎分およそ1万3000本以上ということになります。
1分間にドラム缶1万本以上と考えると、改めてすさまじい量ですね・・・。
また、各温泉の分析書の湧出量を見て、ドラム缶でイメージするとどれぐらいの量か理解しやすいかもしれません。
温泉の多い地域No.1はどこ?
続いては各都道府県で温泉の多い地域について。
これは結構気になる方も多いと思います。
まず地域的に温泉地が多いのは、
- 1位:北海道(244)
- 2位:長野県(225)
- 以下、新潟、青森、福島、秋田、静岡、群馬、鹿児島(それぞれ100以上)
ご覧のような結果になってます。土地の広さ的に北海道は納得かもしれませんね。
また2位は長野県。長野は百名山の数も日本一といわれてますが温泉の数も多いようです。
続いて源泉数が多いのは、
- 1位:大分県(4471)
- 2位:鹿児島県(2785)
- 以下、静岡県、北海道(2000以上)
- 熊本県、青森県(1000以上)
このような結果です。源泉数が多いのは大分県。これもなんとなく納得でしょうか。
特に別府市はいたるところに湯気が出ていている街並みを思い浮かべます。
ちなみに湧出量でも大分県が最も多く、28万5185L/min。流石の量です。
また2位には鹿児島がランクイン。また熊本県も1000以上。
こうやってみると九州がとても多いということが分かります。
温泉の色が付く原因について
温泉の水は通常無色透明ですが、中には白濁したり、青白色や褐色や赤褐色、黒色や緑色などもあります。この色は一体何に由来するのでしょうか。
温泉水の色の原因はいろいろあります。
懸濁物質の色
まず原因の一つは懸濁物質(けんだくぶっしつ)。
懸濁物質とは、水中に浮遊している直径2mm以下の粒子状物質のこと。
これは黄白色の硫黄華や赤黄色の鉄華など、沈澱すると湯の華となるものもあります。
また、温泉水中の微生物がつくる皮膜(バイオマット)により、源泉周辺の岩肌が緑色、白色、茶色などさまざまな色になることもあります。
これでよくみられるのは白い湯の華によるにごり湯でしょうか。乳頭温泉郷の「鶴の湯」なんかはそれにあたりそうです。

イオンによる色
続いては溶存しているイオンによる色です。
特に「遷移金属元素」と呼ばれるものが水に溶けると、水和したイオンが鮮やかな色を示す場合が多く、
例えば2価の鉄イオンは緑青色、コバルトは淡紅色、銅イオンは青色を示すことなどはよく知られています。
ただ、温泉水中の金属イオン濃度は微小であり、このような理由で色がつくことはほとんどないといえます。
イオンによる呈色としては、多硫化物イオンによる黄色の呈色が報告されています。(青色と混ざれば緑色)
※呈色とはある物質が他の物質と反応して色が現れること、または変色すること
この要因により色がついている温泉が岩手県の「国見温泉」や長野県の「熊の湯温泉」のようです。


どちらも黄緑色の美しい温泉ですね。
なお、この色味は「イオンによるもの」+ 後述する「コロイド粒子によるもの」とされているようです。
コロイド粒子による色
もう一つの要因に挙げられるのが、コロイド粒子による色です。
コロイド粒子とは、1ナノメートル〜1マイクロメートル程度の微細な粒子で、液体・気体・固体の中に均一に分散して存在する粒子のことです。
温泉水中に溶存するシリカ(二酸化ケイ素)や硫黄の分子が重合してある大きさ(0.1~0.4μm)のコロイドになると、
まず太陽光の可視光(波長が0.4~0.7μm)のうち青色成分の光が散乱し、波長の長い赤色成分の光は通過させてしまうため、青い光だけが私たちの目に届き青く見えます。
このような微細粒子による短波長の光の選択的な散乱をレイリー散乱といいます。
また、粒子がもう少し大きく(0.4μm程度以上)なると今度は波長の短い光も長い光もともに散乱され、すべての光が目に届くようになり白く見えます。
ような散乱をミー散乱といいます。
※重合とは一つの化合物の二個以上の分子が結合して、幾倍かの分子量の新たな化合物となる反応
要は、コロイドの大きさによって見える色が変化するということですね。
湧出時は無色だったものが、温泉水中の粒子が成長するにつれて、
透明→青色→白色 へと変化していくことが一例としてあるそうです。
この要因による色の変化で名前の挙がった温泉の一つが、大分県の「明礬温泉」。

旅館若杉さんに宿泊した時のものです。
ほんのりブルーなのが分かりますかね?見たときに結構感動した記憶があります。
また、ほかには「由布院温泉」の 泰葉というお宿がきれいなブルーだそう。一度入ってみたいものです。
(ちなみに、ここで紹介した温泉はいくつかのAIの回答から得たものですので、必ずしも正しいものではない可能性があることをご了承下さい)
まとめ:面白く奥深い温泉の世界
以上、今回は
- 日本の温泉の数
- 温泉、源泉数の多い地域
- 温泉の色の秘密
についてのご紹介でした。
皆さんの住んでいる地域の温泉、好きな温泉は入っていたでしょうか?
この記事によって少しでも温泉への興味を持つきっかけを持ってもらえると嬉しく思います。
そして気になる温泉があったらぜひ足を運んでみてください!
また、温泉についての基礎を知れる記事も作成しています。
こちらもぜひあわせてお読みください。
なお、今回記載した内容も温泉の科学 温泉を10倍楽しむための基礎知識!! という書籍を参考にさせていただいております。
より深く知りたい場合はこちらの購入もお勧めです。